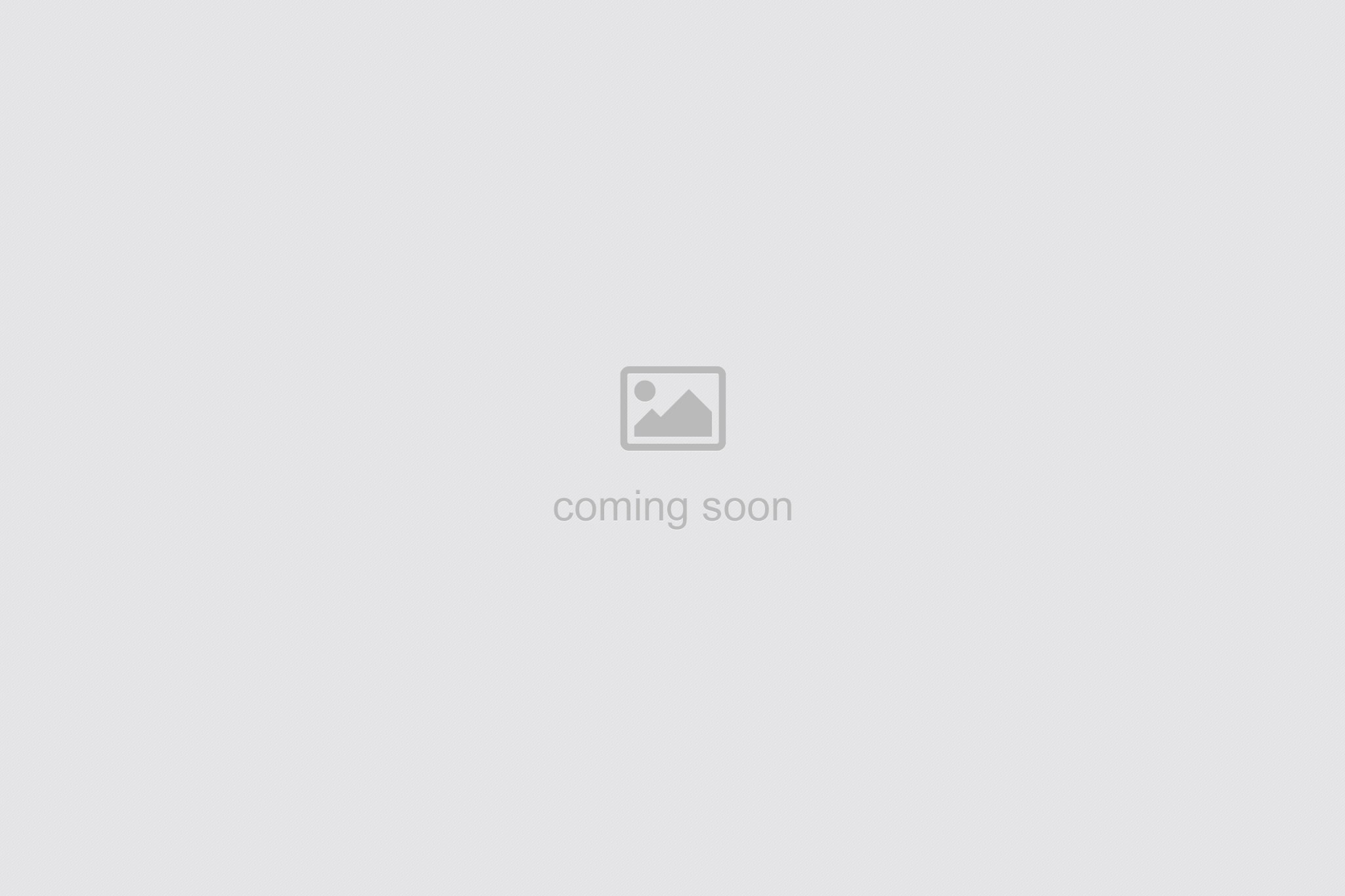ブログ
贈ることば
これから先,皆さんが成人になってからの生き方のことですが,そこで思い出すのは,別府太陽の家の創設者である中村裕博士の言葉で,No Charity but a Chance です.1965年当時障がい者が働くということは誰も考えていませんでした.中村氏は障がい者へは保護でなく働く機会の提供が大切だと訴え,障がい者が働く施設を創設しました.時代は変わり,障害者総合支援法が施行され,国連の障害者権利条約を批准し,障がい者の様々な権利が保障されて福祉の制度が細かく構築される時代になりました.
障がい者の社会参加は1981年の国際障害者年のスローガンの「完全参加と平等」でしたが,それから44年を経た今日,完全参加や平等は達成されているでしょうか.さらに2020年の東京オリンピックのテーマは「多様性と調和」でした.50年前からイベントごとのテーマは変わってもスローガンが言わんとしていることは何も変わりません.つまり,「一緒に」ということです.「一緒」ということは,「もの,こと」「時間」「思い」の三を共有できることが条件です.障がい者と一緒に暮らす,働く,集うには単にそこに障がい者がいるだけではなくこの三つが揃うことが必要です.障害者雇用促進法という制度によって雇用が義務付けられています.その達成率はいつになっても半分以下ですが,会社や組織の中に障がい者が存在することがこの法律の趣旨でなく,そこで一緒に働くという考えが必要です.
障がい者の社会参加には障がい者の「居場所と出番」が必要です.居場所というのは,そこにいていいですよ,そこは私たちと一緒ですよということで,出番というのは社会の中の出番であなたが任せられている仕事があるという意味です.つまり,社会の中で必要とされている存在です.障害者総合支援法は障がい者の自立と社会生活,社会参加のための制度を作り,多くの障がい者の生き方を支援しようとしています.が一方で,それは障がい者の社会参加を仕組みという枠に閉じ込めようとすることでもあります.障害者就労移行支援では本人の意思決定の下に自由に仕事を選ぶことができるとしながらも,暗黙の障がい者枠があることを組織は見て見ぬふりをしています.つまり,一緒に働きましょうではないのです.この現象は障がい者イクオール能力が劣るという社会通念がどこかにあるからではないでしょうか.つまり,背景にある雇用してやっているという組織側の考えがまだまだ障がい者の存在,共生社会に対して成熟していない現実があるようです.
以前に比べると障がい者が働きやすくなりました.それはいろいろな法律に基づく制度が構築されたためです.言い換えれば,制度によって障がい者の働く権利が支えられているのであるなら,制度がなかったら障がい者の働く場はないのかもしれません.さて,いつまで制度に頼った福祉が続くのでしょうか.我が国が資本主義国家としてもしアメリ合衆国の文化である「機会の平等」を踏襲するのなら制度に頼るしかありません.しかし,欧州のように福祉は社会で支えるという「結果の平等」を導入するのであれば,制度でなく文化としての障がい者支援が,かなりの年月を経て成り立つかもしれません.障がい者の存在がいても当たり前という文化ができれば,制度という枠組はなくてもよくなります.かつての排除の論理から共生の論理へと変換するには,幼児の時代の共生の現実が,分離教育をなくしてインクルーシブの中で成長することが必要です.大人の社会はそれを後押しして,会社や組織,あるいは地域の中に障がい者がいるのは自然でありごく普通という文化を築くことを期待したいと思います.